アレキサンドライト
|
 |
||
| 鉱物名 | クリソべリル | 和名 | 金緑石 |
| 化学組成 | BeAl2O4 | 誕生石 | 6月、7月(米) |
| 結晶系 | 斜方晶系 | 硬度 | 8.5 |
| 比重 | 3.71 | 宝石言葉 | 高貴、情熱 |
| 屈折率 | 1.74〜1.75 | 語源 | 下記項目を参照 |
| 一般処理 | 加熱 | 色 | 深緑、暗赤色(変光性) |
価格例
アレキサンドライトという名前の由来
アレキサンドライトは1830年、ロシア帝国ウラル山脈のエメラルド鉱山で発見されました。この鉱物は不思議なことに、 昼間に見たときは緑色だったはずなのに、持ち帰り夜ローソクの光の下で見てみると、赤色に変わっていたのです。 「これは神のいたずらに違いない。」と鉱夫たちの間で大騒ぎになりました。そして、これは大変な石だという事で、 当時のロシア帝国皇帝ニコライ1世に献上される事になりました。その日4月29日は皇太子アレキサンドル二世の12歳の誕生日だったため、 この非常に珍しい宝石にアレキサンドライトという名前がつけられました。 また、軍服の色が赤と緑だったロシア人にとっては、お守りとして特別な価値のある石となりました。
色温度について
光源の色の性質を簡単に表示するモノサシのひとつに「色(いろ)温度」という考え方があります。
金属を熱していくと、次第に赤味を帯びた光を発するようになり、温度を上げていくと赤味が取れて黄色くなり、 次第に白っぽい光を発するようになります。さらに加熱すると、青味がかった光をします。 また、地学の授業で星の色と温度について習ったことがあると思います。例えば、青色の星は温度が高くて、 赤色の星は温度が低いと言うものです。
こういった具合に、温度と色とには一定の関係があることから、色温度がモノサシによく使われるようになりました。 色温度の単位には「K(ケルビン)」が用いられ、数値と色のおおまかな関係は次の表のようになっています。
自然光と人工光の色温度(K)
| 【自然光】 | 日の出・日の入り ▼(約2,500K) |
日陰・曇天 ▼(約7,000K) |
||||
| 【人工光】 | 家庭用電球 ▼(約2,800K) |
▼スピードライト(約5,500K) | ||||
| ろうそく ▼(約1,900K) |
写真用電球 ▼(3,200K) |
▼デイライト(5,500K) | ||||
| 2,000K | 3,000K | 4,000K | 5,000K | 6,000K | 7,000K | 8,000K |
| 赤味の強い光 | 白 | 青味の強い光 | ||||
この表を見るとわかるように、確かに昼の太陽光は青み成分が多く、白熱電灯は赤み成分が多いことがわかります。
宝石の色
| 1.反射 | 光が宝石に照射たとき、宝石の表面で光が反射されて、目に届いた色がその宝石の色となります。全ての色を反射した場合は白、全く反射しない場合には黒に見えることになります。 |
| 2.吸収 | 反射と深く関わっているのですが、反射しない光のことを指します。宝石によって吸収されることによって、 吸収された以外(反射として目に届く光)の光が宝石の色ということになります。 |
2つの要素の関係は、反射か吸収かということです。反射しなければ吸収。吸収しなければ反射が行われるのです。
光のスペクトル
光というのは、電磁波の一種で人間の目に見える可視光線のことをいいます。
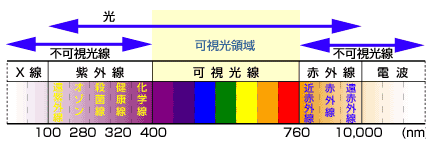
可視光線のをはずれた紫側を紫外線、赤側を赤外線といいます。
光の吸収
ここでは可視光線の部分の宝石による吸収について説明します。下記の可視光線のスペクトルの黒い部分がそれぞれの宝石が吸収する可視光線の周波数です。
| ルビーが吸収する光 | アレキサンドライトが吸収する光 |
| 青から紫部分と、黄、緑の部分を吸収 | 青から紫部分と、黄色部分を吸収 |
ルビーは、反射する光がほぼ赤色要素ばかりなので、必然的に赤色に見えます。
アレキサンドライトは反射する光に赤色要素と、緑色要素の両方が平均的にあるため、 上の色温度の表から見てもわかるように、5000K以上の色温度の光が照射されると、光に青み成分が多く存在してるため、 緑みが赤みを上回って緑色に見えます。逆に、5000K以下の色温度の光が照射されると、光に赤み成分が多いため、 赤みが緑みを上回って赤色に見えるのです。
以上の説明でわかっていただけましたか?
しかしながら、光が吸収されない赤と緑の部分が均等でないと、きれいに色が変わりません。 この理想的な均等さがアレキサンドライトの価値をきめます。
アレキサンドライトの価値基準
アレキサンドライトは、鉱物特性上インクルージョン(不純物)が入りやすいので、出来るだけインクルージョンの少ないものを選ぶべきです。しかし、それよりもアレキサンドライトの価値基準の最大の注意点は、色の変色性にあります。どれだけはっきりと緑から赤へと変色するかが、全てなのです。赤と緑の要素のバランスの本当にいいものは、ちょうど5000Kぐらいの色温度の照明の下でみると、輝きに赤と緑のモザイクが見えるはずです。その次に注意すべきことは色合いです。よく赤はルビーに緑はエメラルドに遠く及ばないと多くの書籍に書いてあります。しかし、それぞれの石に劣るとはいえ十分きれいな色をしている石も多く存在します。その中でも、赤が茶色っぽいものや緑がくすんでいるものは避けるべきです。
まとめますと、アレキサンドライトの重要な要素の順に
- 色の変わり具合(変色性のバランスも含めて)
- 赤と緑のそれぞれの色合い
- インクルージョン
- 大きさ(ct)や形(大きいものでは、ラウンドカットは希少)
産地別傾向
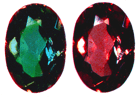 ブラジル産 |
アレキサンドライトの主要産出国のひとつ。ミナスジェライス州が世界的に有名な産地で、 現在入手可能なアレキサンドライトとしては最高品質といえます。変色がはっきりしているものが多く、 色合いもきれいでインクルージョンも比較的少なく透明度が高いといえます。 ただ、5ct以上の大きい石の産出となるとほとんどありません。 |
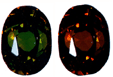 スリランカ産 |
ラトナプラ地区が有名な産地で、黄色みがかったグリーンを呈しているものが多く、赤色への変色が弱いのが特徴です。 ロシア産よりも大きなものが産出されますが、アレキサンドライトの価値としては低く、 色の変わらない単なるクリソベリルとしか呼べないものも多く産出します。 しかしながら、大粒のアレキサンドライトが多く産出されます。 |
| ロシア産 | 一般的に、スリランカ産のものよりブラジル産の方が、昼光での緑色に強い青味が入り美しく、 人工光でも劇的に赤色に変わりますので、高品質だとされています。 そして、アレキサンドライト発祥の地でもあるロシアのウラル産アレキサンドライトは、緑色と赤色の変色のバランスが良く、 非常に上品で美しく、ブラジル産をもしのぐ最高品質なのです。 しかし、インクルージョンが多いものが大部分で、きれいな石の産出は限られています。 加えて、残念なことに元々大きな宝石質原石が産出しない上に、殆ど採り尽くされてしまったという事で、 今ではかなり入手が困難になってしまい非常に高価です。 そのため、現在では幻のロシアン・アレキサンドライトといわれています。 |
| タンザニア産 | タンザニアのマニャラ湖の西岸の鉱山で、クリソベリルやその変種のアレキサンドライトとキャッツアイも産出します。 アレキサンドライトは少量しか産出しないのですが、かなり良質なものも採れ、 最近では手に入らなくなった上品で、最高品質のロシア産に似ているといわれています。 |
| マダガスカル産 | 最近マダガスカルでは、かなり色々な地方で色々な種類の宝石の産出がすすんでおり、 一般的な宝石のほとんどが産出されています。アレキサンドライトもその1つで、良質な石も産出されてはいますが、 なにぶん最近採掘がはじまったばかりということもあり、データをとることが出来るほどではありません。 しかしながら、今後最も期待できる産地であると言えるでしょう。 |